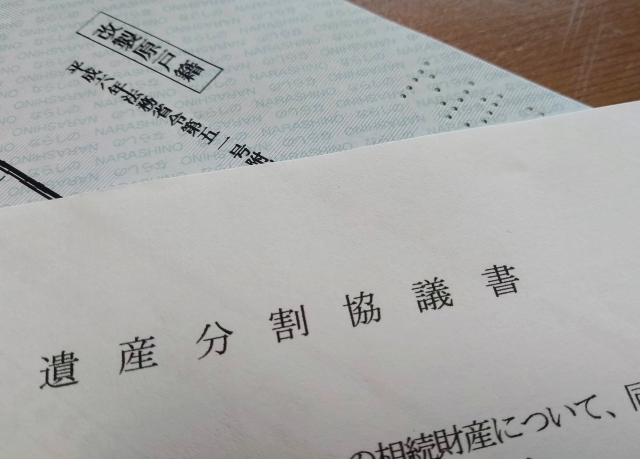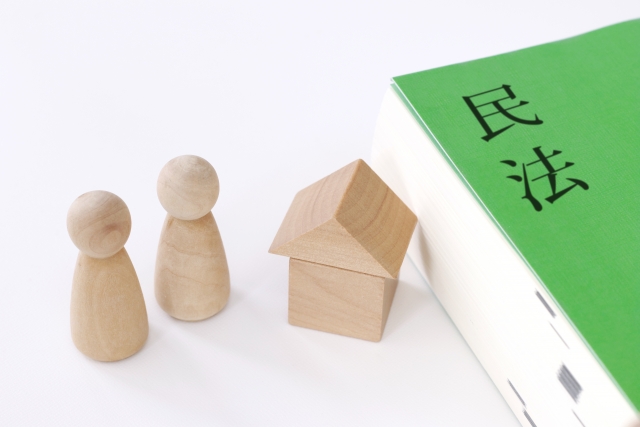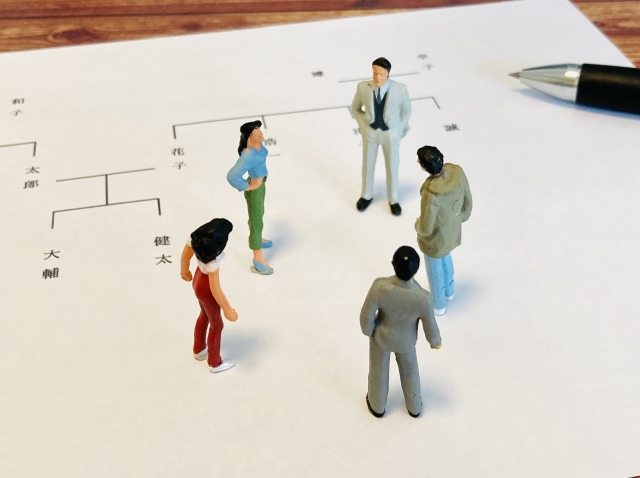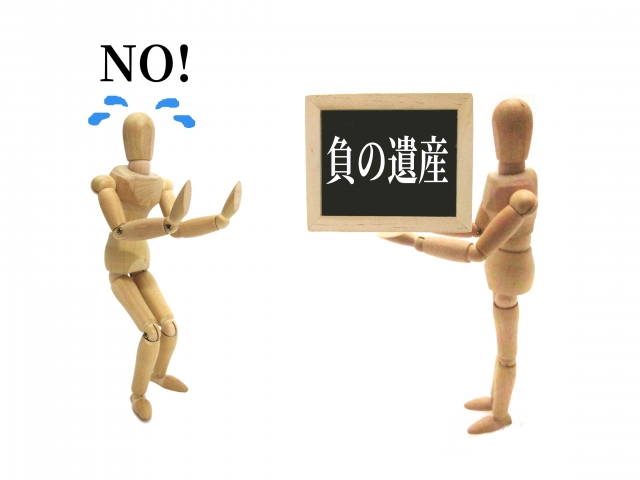遺留分という制度は何のためにあるのか
誰でも、自分の財産を遺言によって自由に処分することができますが、この自由が無制限に認められると、相続による遺産の取得を期待していた遺族(法定相続人)としては困ったことになります。
遺留分制度は、遺言の自由を尊重しつつ、一部の法定相続人に対して最低限度の相続財産を保障することで、遺族の生活を守ることを目的としたもので、この最低限度の保障部分のことを「遺留分」と呼んでいます。
これらの力関係を図示すると
遺留分 > 遺言・生前贈与 > 法定相続
となり、遺言よりも強いのが「遺留分」ということになります。
遺留分が侵害された場合に、何ができるのか
被相続人の遺言(遺贈)や生前贈与によって遺留分が侵害された場合、その不足分に相当する金銭の支払いを、遺留分を侵害した者(遺言によって多くの財産を受け取った受遺者や、被相続人から多額の生前贈与を受けた受贈者)に対して請求することができ、これを「遺留分侵害額請求」と呼んでいます。
この請求権は、遺留分権利者が、相続の開始と自身の遺留分が侵害されていることを知ったときから1年以内、または相続開始から10年以内のいずれか早い時期に行使する必要があります。
なお、遺留分を侵害するような遺言が作成された場合に、この遺留分侵害額請求権が発生しますが、遺言自体が無効とされるわけではありません。つまり、遺留分を侵害するような内容の遺言も法的には有効な遺言となります。
遺留分侵害額請求と金銭債権
「遺留分侵害額請求」は、2019年7月1日に改正民法が施行されるまでは「遺留分減殺請求」(いりゅぶんげんさいせいきゅう)と呼ばれており、改正民法によって呼び名が変わると共に、その法的性質も変わることになりました。
まず、改正前民法の「遺留分減殺請求」は、遺留分を侵害された額を限度として、侵害された財産そのもの(不動産などの現物)を取り戻す物権的な権利とされていました。
このため、例えば、不動産が遺贈されたケースにおいて遺留分減殺請求がなされると、不動産が自動的に請求者と義務者の共有状態となり、その後の管理や売却を巡って新たなトラブルとなることがありました。
この点、改正後民法の「遺留分侵害額請求」は、単に金銭の支払を求める金銭債権へとその法的性質が変わりましたので、不動産などの共有関係が発生することはなく、金銭での清算による早期解決につながっています。
もっとも、遺留分侵害額請求の金銭債権化により、発生した金銭債権は、請求権とは別に消滅時効(行使できることを知った日から5年)にかかります。つまり、請求権自体の1年または10年という期間制限をクリアした後は、一般的な債権の時効についてケアする必要があります。
遺留分を請求できるのはだれか(遺留分権利者)
遺留分侵害額請求権を行使できる遺留分権利者は、被相続人の兄弟姉妹以外の法定相続人に限定されています。
具体的には、被相続人の①配偶者、②子(代襲相続人を含む)、③直系尊属(父母や祖父母など)が該当します。
つまり、被相続人の兄弟姉妹は法定相続人ではありますが、遺留分は認められていませんので、遺言で兄弟姉妹に全く遺産を与えないとしてしまえば、兄弟姉妹は何も受け取ることはできません 。
(2025年8月18日)