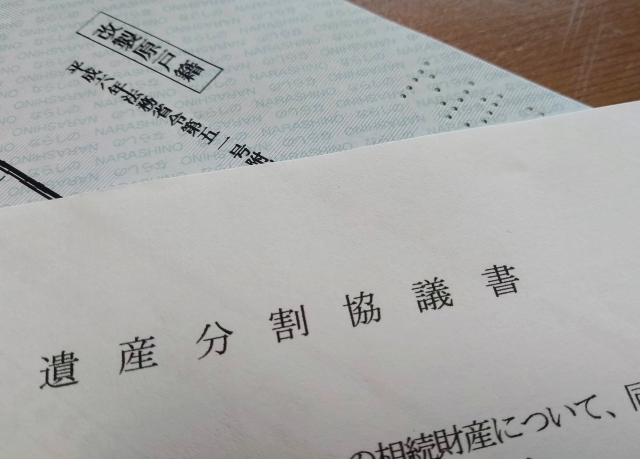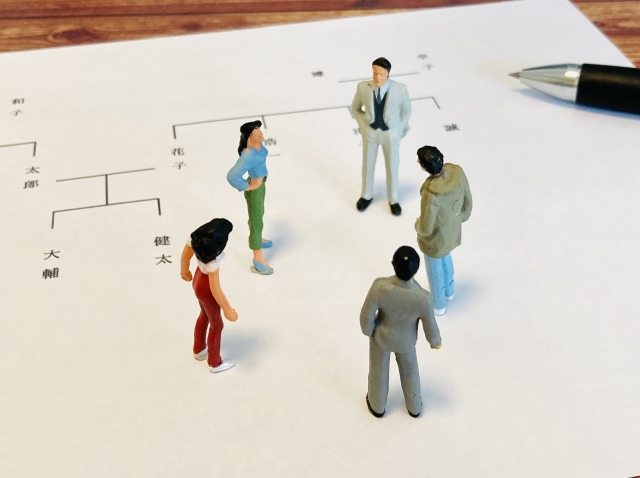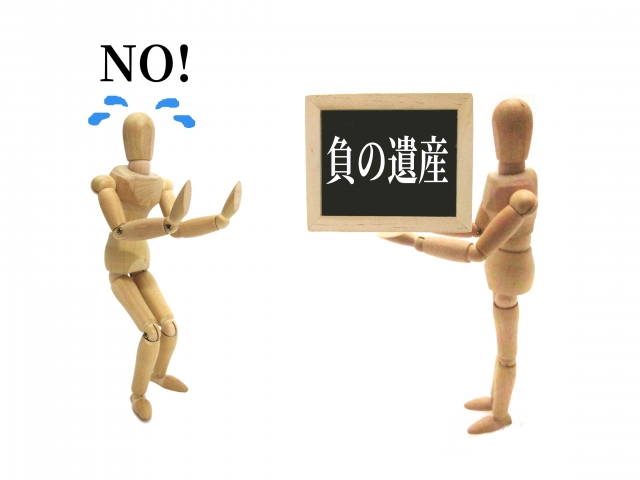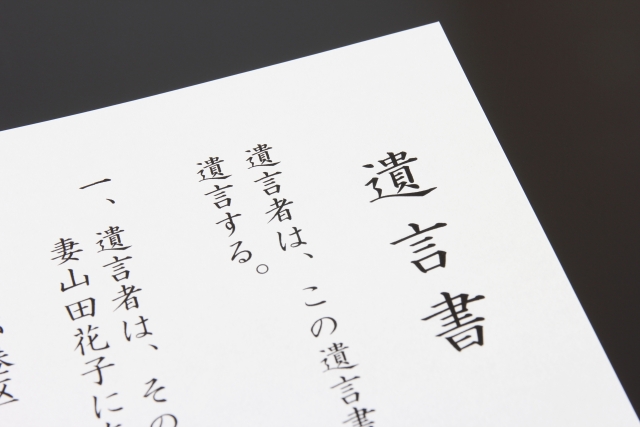〔遺言が有効となるための2つの要件〕
遺言を作成するのは高齢者が多くなりますが、例えば認知症などで判断力が乏しくなっている方が作成した遺言書は法律的に有効と言えるのでしょうか。
この点、遺言が有効であると言えるためには、民法で2つの要件が必要とされています。
- 遺言者が15歳以上であること(民法961条)
- 遺言者に意思能力があること(民法3条の2)
この2つの要件を充たしていれば、遺言者は、遺言の意味を理解して、自分が亡くなった後にどのように遺産が受け継がれるかを自ら決めることができると考えられており、これを遺言能力といいます。
〔遺言者が15歳以上でなければならないこと〕
通常の契約などにおいては、判断力が乏しい方を類型化して保護するために、未成年者、後見・保佐・補助という制限行為能力者制度があり、単独で契約をした場合の取消権などが認められています。
しかしながら、遺言には、これらの未成年者、後見・保佐・補助による保護制度の適用はありませんので(民法962条)、15歳に達していれば、未成年者も成年被後見人も被保佐人も被補助人も、親権者などの保護者の同意なしに、単独で有効に遺言ができます。
ただし、成年被後見人が遺言をするためには、①事理を弁識する能力を一時回復しているときに、②医師2人以上の立会いのもとに行う必要があるとされており(民法973条)、この立会いを欠く遺言は無効となります。
〔遺言者に必要な「意思能力」とはどのようなものか〕
遺言者に必要な「意思能力」がどの程度なのかについては、法律で具体的に定められたものはありませんし、年齢や病名で一律に決められるものでもありません。
この点、実際の裁判例では、①遺言の具体的な内容(遺産の額や質から見た重大さ、内容の複雑さ)、②遺言時の遺言者の判断力の程度(入通院状況、病名など)、③遺言作成の理由や作成に至った経緯という3つのポイントを総合的に考慮した上で、遺言者が遺言の内容を理解し、遺言をするという自己決定ができたかどうかが判断されています。
〔意思能力を判断するためのポイント① ~遺言の内容~〕
遺言に関する意思能力の有無は、遺言の内容を理解して自分で判断できているかどうかの問題ですので、遺言の内容が簡単なものであれば遺言者がそれを理解するのも簡単といえ、意思能力が認められやすくなります。
他方で、複雑な内容の遺言や重大な意味を持つ内容の遺言であれば、その具体的な意味を正確に理解できるためにはそれなりの判断力が必要になりますので、意思能力は比較的認められにくくなります。
したがって、遺言内容自体がどれだけ複雑・重大なものかは、遺言の有効・無効の判断に影響することになります。
〔意思能力を判断するためのポイント② ~遺言者の判断力~〕
遺言書を作成したときの遺言者の精神状態がどのようなものであったかは当然重要な判断要素になります。
遺言書を作成したときに遺言者が精神疾患などによって入通院をしていれば、そのときの医師による判断を確認することもできますし、その時期における医療記録なども重要な資料になります。他方で、遺言書を作成したときに特に入通院などしていない場合には、遺言書作成後に事後的にでも医学的な診断を行ったうえで、遺言書作成時の精神状態をさかのぼって推認することになります。
また、医学的な診断だけでなく、遺言者が、遺言書を作成していた時期に異常な行動などの判断力に疑問が生じるような言動をしていたかどうかも一つの判断要素となります。
〔意思能力を判断するためのポイント③ ~遺言作成の理由・経緯~〕
遺言者が遺言をしようと考えた理由がどのようなもので、その理由自体に一定の合理性があり、かつ、実際に作成された遺言の内容と作成理由がマッチしていれば、遺言作成に至った経緯に合理性があることになり、意思能力が認められやすくなります。
逆に言えば、遺言書の作成に至った経緯に合理性がなく、遺言の内容も遺言者のそれまでの生活状況などからして合理性を欠く内容になっていれば、遺言者の意思能力の乏しさを示す一つの要素となります。
〔遺言能力に関する争いをあらかじめ避けるための方法〕
①公正証書遺言の作成
公正証書遺言は、公証人が直接に遺言者の言動を確認する段取りになっていますので、遺言者に「明らかに遺言能力がない」わけではないことが一応他人によって確認された上で作成されています。
したがって、公正証書遺言により遺言が作成されていれば、(必ず遺言能力ありとなるわけではありませんが)遺言能力があったことが強くうかがわれることになります。
②医師の診察を受けておく
遺言書作成と近い時期(前後いずれでも)に、医師の診察を受けて、認知症ではないこと、あるいは認知症であるとしても軽度であることを記録に残しておくことが効果的です。
後のことを考えて、このような医師の診断を受けた上で診断書を発行してもらうと共に、診断経過が分かるようにするためにカルテの写しを取り寄せておくようにしましょう。
もちろん、認知症が通常問題とならないような比較的早い年齢(70歳になる前くらい)で(自筆証書であっても)遺言書を作成しておけば、そもそも認知症による判断力不足についての争いが生じにくくなりますので、より安心です。
(2023年2月1日)