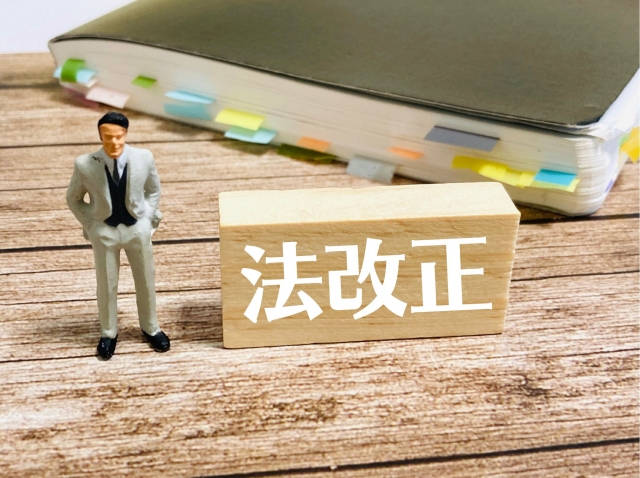総会における動議とは
管理組合の総会では、基本的に、事前に招集通知に記載された議案について、審議と議決が行われます。
しかし、ときに、議事として予定されていなかった新たな提案、いわゆる「動議」が、総会出席者から出されることがあります。
では、この動議が出された場合に、議長はどのように対応しなければならないのでしょうか。
「総会進行」に関する動議の扱い
議長の不信任に関する動議など、総会の進行に関する手続的な動議については、議長は、そのつど議場に諮って決める必要があります。
議案の目的と無関係な新たな議案が動議として出された場合
そもそも、区分所有法37条1項では「集会においては、招集通知によってあらかじめ通知した事項のみ決議することができる」とされていますが、同条2項で、動議内容が普通決議事項の場合は規約で別に定めてもよいとされています。
そのため、普通決議事項に関しては、「あらかじめ通知した事項でなくても決議ができる」旨の規約が定められていれば、議案の目的と無関係な動議も認められることになり、議長は、この動議を議場に諮る必要があります。
もっとも、このような「あらかじめ通知した事項でなくても決議ができる」旨の規約は、標準管理規約も含め、一般的な管理規約では定められていません。
したがって、一般的な管理規約の場合、あらかじめ通知された事項だけ決議できることになりますので、議案の目的と無関係な新たな議案が動議で出されても、あらかじめ通知された事項ではないため、これを決議することはできません。
以上から、一般的な管理規約の場合であれば、議長は、議案の目的と無関係な新たな議案の動議を取り扱わずに審議を進めなければなりません。
議案の目的と関連する修正動議が出された場合
これについては、普通決議事項と特別決議事項で分けて考える必要があります。
①普通決議事項の場合
普通決議事項については、区分所有法上、「会議の目的たる事項」が通知されていれば足りるとされています。
ここで、「会議の目的」というのは、例えば、「理事選任の件」とか、「管理費値上げの件」など、いわば議事のタイトルのことです。
とすると、普通決議事項において、通知された議案の目的と関連する修正動議が出された場合は、基本的には会議の目的が共通ですので、「あらかじめ通知した事項」になり、動議が認められることが多いと言えます。
したがって、議長は、普通決議事項の議案の目的と関連する修正動議については、基本的に、審議および議決を行わなければなりません。
②特別決議事項の場合
特別決議事項については、区分所有法上、「会議の目的」だけでなく、「議案の要領」の通知も必要とされています。
例えば、「会議の目的」(つまり、タイトル)が「規約改正の件」であれば、その「議案の要領」というのは、「規約○条を~に改正する」といったものになります。
とすると、特別決議事項において、通知された議案の目的と関連する修正動議が出された場合は、会議の目的が共通であっても、議案の要領自体を修正する動議となっていることが多く、基本的には、「あらかじめ通知した事項」とは言えません。
したがって、特別決議事項の修正動議については、通知された「議案の要領」と実質的にみて同一と言えるような事情がなければ、修正動議としては認められず、議長は動議を取り扱わずに審議を進めなければなりません。
動議が認められる場合の決議方法
仮に、動議が認められる場合、書面での議決権行使者は、動議の議決には参加できませんので、棄権扱いとなります。
そのため、動議については、総会の現場にいる区分所有者と委任状を提出した区分所有者の数で決議要件の判断をすることになります。
もっとも、委任状の場合、動議が出た場合も含めて委任していると言えるかどうか悩ましいところですので、委任状に、動議が出た場合の判断も含んで委任する旨を記載しておくのも一つの方法です。
(2025年4月13日)