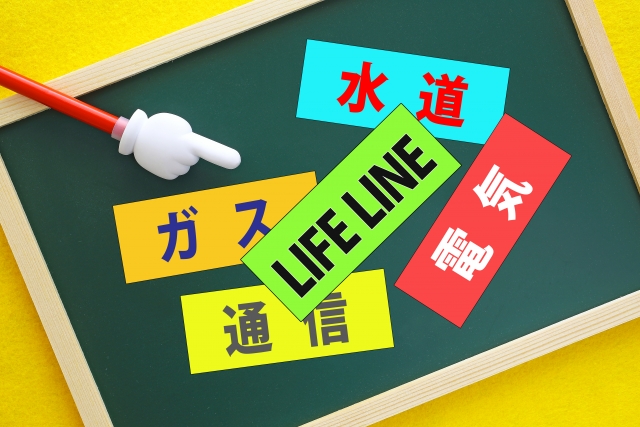〔改正前の隣地使用権の定め〕
改正前の民法では、土地の所有者は、民法で定められた一定の場合(建物の築造や修繕など)、必要な範囲で隣地の使用を請求できると定めており、これを「隣地使用権」と呼んでいました。
ところが、改正前の隣地使用権は、「境界又はその付近において障壁又は建物を建造し又は修繕するため必要な範囲」に限定されており、また、隣地使用権を行使する方法については具体的な定めもありませんでした。
〔改正のポイント ~全体像~〕
- 隣地の使用ができる範囲が拡大しました
- 隣地使用権の性質が、「使用請求権」から「使用権」へ変わりました
- 隣地の使用方法は、損害が最小限になる方法でなければなりません
- 隣地使用にあたっての手続として通知が必要です
〔隣地使用ができる場合〕
土地の所有者は、次の①~③の目的のために必要な範囲で隣地を使用することができますが、住家については、その居住者の承諾がなければ、立ち入ることはできません(209条1項)。
①境界やその付近における障壁・建物その他の工作物の築造・収去・修繕
②境界標(土地の境界を示す目印のこと)の調査、境界に関する測量
③越境してきた隣地の「枝」(「根」は含まれません)を、民法の規定に従って切り取る
〔隣地使用権の性質と自力救済〕
隣地を使用できる権利について、単に「使用することができる」(209条1項)という文言になりましたので、法的な性質が「使用請求権」ではなく「使用権」になっています。これによって、土地の所有者は、要件が充たされていることは当然の前提ですが、隣地所有者などの承諾がなくても隣地を使用できることになります。
もっとも、だからと言って、隣地所有者などが隣地使用に対する妨害を行う場合に、土地の所有者が実力を行使して妨害を排除することは認められません(いわゆる自力救済の禁止)。この場合、土地の所有者としては、妨害行為の差止めなどの手続を経て、隣地使用権を行使しなければなりません。
〔隣地の使用方法〕
隣地を実際に使用するにあたって、使用の日時・場所・方法は、隣地の所有者や隣地を現に使用している者(賃借人など)のために損害が最も少ないものを選ばなければならないとされています(209条2項)。
なお、隣地の使用に伴って隣地の使用者に損害が生じた場合には、償金を支払う必要があります(209条4項。この内容については、改正前と同様です。)。
〔隣地使用にあたっての手続としての通知〕
隣地を使用する際は、あらかじめ、その目的・日時・場所・方法を、隣地の所有者および隣地を現に使用している者に通知しなければなりません。ただし、あらかじめ通知することが困難なときは、隣地の使用を開始した後、遅滞なく通知すればよいとされています(209条3項)。
したがって、原則としては、まず使用する旨の通知を行い、隣地の所有者や使用者が対応するのに必要な合理的な期間を置いた上で使用をするという流れが必要です。
なお、隣地所有者が特定できなかったり、その所在が不明であるような場合は、使用後に、隣地所有者やその所在が判明したときに通知すれば足り、公示による通知(民法98条)の方法をとらなくてもよいとされています。
(2022年12月9日)